現代人の多くが悩まされている「肩こり」。その対策として市販薬や湿布薬に頼る人も少なくありません。特にロキソニンやモーラステープは、「肩こりに効く薬」として多くの人に使用されていますが、本当に効果があるのでしょうか?この記事では、ロキソニンやモーラステープの薬理作用から、使用方法、副作用、そして効きやすい肩こりのタイプまで、医学的な視点と実体験を交えて徹底的に解説します。肩こりに悩むすべての人に、科学的根拠に基づいた正しい情報をお届けします。
肩こりとは?その仕組みと主な原因
肩こりは、単なる疲れではなく、筋肉・血流・神経が関わる複合的な症状です。肩まわりの痛みや重だるさは日常生活に支障をきたすだけでなく、頭痛やめまい、不眠などを引き起こすこともあります。このセクションでは、肩こりの成り立ちや原因について、医学的な視点から詳しく解説します。
肩こりのメカニズム
肩こりは、筋肉の持続的な収縮により血流が低下し、酸素や栄養が不足することで発症します。特に僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋などの筋肉は、姿勢を支えるために長時間使われ続けることが多く、疲労しやすい部位です。疲労した筋肉には老廃物が蓄積し、神経を刺激することで痛みや重さ、こわばりといった症状が現れます。また、筋膜の癒着や神経過敏も、肩こりの慢性化に関与します。
肩こりとは、首から肩・背中にかけての筋肉(主に僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋など)が過剰に緊張し、痛み・重だるさ・張り感などの症状が現れる状態を指します。慢性的に肩がこる人は、血行不良によって筋肉に酸素や栄養が行き渡らず、老廃物が滞留し、それがさらなる筋緊張と炎症を引き起こす悪循環に陥っています。
現代人に多い肩こりの背景
現代社会では、パソコンやスマートフォンの長時間使用が肩こりの主因となっています。とくに画面をのぞき込む姿勢や、背中を丸めて座る「猫背姿勢」は、首や肩に大きな負担をかけます。また、通勤や育児、ストレスによる自律神経の乱れも、筋緊張の一因となります。運動不足により筋力や柔軟性が低下している人も多く、肩こりのリスクが高まっているのが現代人の特徴です。
とくに現代社会では、長時間のデスクワーク、スマートフォンの操作、ストレス、運動不足といった生活習慣が肩こりを慢性化させる主な原因となっています。姿勢の乱れも関与しており、猫背や巻き肩によって肩甲骨周辺の筋肉が常に引き伸ばされ、緊張が持続しやすくなるのです。
肩こりに潜む疾患の可能性
慢性的な肩こりの中には、整形外科的あるいは神経内科的な疾患が隠れていることもあります。たとえば頚椎症性神経根症では、神経圧迫による肩こりとともに腕のしびれや筋力低下を伴うことがあります。胸郭出口症候群では、腕のだるさや冷感、握力低下を伴うこともあり、単なる肩こりとは区別する必要があります。こうした症状がある場合には、薬や湿布での対処では不十分であり、早めに専門医の診察を受けることが重要です。
肩こりの中には、単なる筋肉疲労だけでなく、頚椎症、胸郭出口症候群、自律神経失調症など病的原因が背景にある場合もあり、症状が強い、片側に偏る、しびれを伴うなどの異常がある場合は医療機関の受診が必要です。
肩こり、頭痛を和らげるおすすめのストレッチとマッサージ
首から肩甲骨の痛みの原因と今すぐできる対処法
肩こりを撃退!簡単ストレッチで予防する方法と効果的なエクササイズ5選
ロキソニンとは?肩こりに対する作用機序
ロキソニン(一般名:ロキソプロフェンナトリウム)は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に分類される解熱鎮痛薬です。一般的には、頭痛や歯痛、生理痛、腰痛、関節痛などさまざまな痛みに対して使用されますが、肩こりに対しても一定の効果が期待されています。
ロキソニンの肩こりへの適応と限界
肩こりが筋肉の炎症や一時的な過緊張によって引き起こされている場合、ロキソニンは痛みやこわばりを緩和するのに有効です。特に、「急性期の肩こり」や「炎症を伴う筋肉x痛」などでは、ロキソニンの内服により症状が軽減されやすい傾向にあります。ただし、慢性的な肩こりや、筋膜・姿勢由来の根本的な問題には、ロキソニン単独では対応しきれないケースが多いため、物理療法やストレッチとの併用が望ましいとされています。
ロキソニンSと医療用ロキソニンの違い
成分、成分量、添加物、錠剤の大きさ、剤形は同じです。異なる点としては、ロキソニンSは錠剤に割線、刻印が入りません。
出典:ロキソニンSに関するQ&A
ロキソニンテープは肩こりに効く?慢性的な痛みへの効果、使い方、副作用まで専門解説
肩こりからくる頭痛にロキソニンは効果があるのか
肩こりの根本的な改善にロキソニンテープは効果的なのか?
モーラステープの特徴と肩こりへの使用
モーラステープは、ケトプロフェンを有効成分とする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を含んだ外用消炎鎮痛テープ剤で、整形外科領域で多く処方されている医療用湿布薬の一つです。炎症や腫れを伴う関節痛や筋肉痛に対して高い効果が期待されており、肩こりに対しても一部のケースでは有効です。ただし、モーラステープはその薬理作用や副作用の特徴から、使用に際して注意点も多く存在します。
モーラステープの薬理作用と成分構成
モーラステープの主成分であるケトプロフェンは、体内のCOX酵素を阻害することでプロスタグランジンの合成を抑制し、痛みと炎症を抑える作用を持ちます。外用薬として経皮吸収され、皮膚から局所へ直接有効成分が届くため、内服薬に比べて全身性の副作用が起こりにくいのが特徴です。
モーラステープはジェル状の基剤により、密着性と吸収性が高められており、持続的な薬効が期待できます。また、1日1回貼付で済む点も患者の利便性に寄与しています。ただし、成分に含まれる光感受性物質による副作用のリスクがあるため、使用部位を紫外線にさらさない配慮が必要です。
他の湿布薬と何が違うのか
一般的な湿布薬とモーラステープの大きな違いは、薬理効果の強さと副作用の出やすさにあります。たとえば、サロンパスなどの市販薬は冷感・温感成分によって一時的な鎮痛を得ることが主目的であるのに対し、モーラステープは抗炎症作用を有する医療用医薬品です。
また、モーラステープには筋肉や関節部への深達性が高く、内服薬と同様の強い鎮痛効果が期待されます。これはとくに炎症を伴う急性の肩こり、筋肉痛、外傷性の肩の痛みに対して有効です。
光線過敏症や皮膚炎のリスクについて
モーラステープで特に注意が必要なのは、光線過敏症です。ケトプロフェンには紫外線に反応しやすい性質があり、貼付後に日光を浴びると皮膚が赤く腫れたり、水疱ができる重度の皮膚炎を引き起こすことがあります。これを避けるためには、使用期間中および使用後も一定期間は貼付部を直射日光に当てないよう、長袖で覆う・日光を避けるなどの対策が必要です。
また、かぶれ・かゆみなどの接触性皮膚炎も比較的起こりやすく、特に皮膚の弱い人やアレルギー体質の人は使用前にパッチテストを行うことが推奨されるケースもあります。副作用が出た場合は、すぐに使用を中止し医療機関を受診することが求められます。
ロキソニンとモーラステープの併用は可能か?
肩こりが強いとき、「ロキソニンの内服とモーラステープの併用をしても大丈夫か?」という疑問を持つ方も多いでしょう。実際、病院ではロキソニン錠(内服)とモーラステープ(外用)を併せて処方するケースは珍しくなく、一定の条件下では併用が可能です。ただし、自己判断での併用にはリスクもあるため、ここではその医学的な根拠と注意点について詳しく解説します。
作用機序と相互作用の観点から
ロキソニンとモーラステープはいずれもNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)に分類され、どちらもプロスタグランジンの生成を抑制することによって炎症と痛みを軽減します。内服と外用で作用部位が異なるため、重複して使うことで効果が高まるという側面もあります。
しかしながら、体内に取り込まれるNSAIDsの総量が増えるため、胃腸障害や腎機能障害といった全身性の副作用のリスクも高くなります。特に、長期併用や高齢者・腎疾患のある方では慎重な判断が求められます。
医師の診断が必要なケース
ロキソニンとモーラステープの併用は、必ず医師の診察のもとで行うのが原則です。単なる肩こりであっても、痛みの背景に疾患(頚椎症・神経圧迫・リウマチなど)が隠れている場合には、薬剤選択や用量が大きく異なるからです。
医師は患者の体質、既往歴、現在の服用薬、年齢、生活状況を総合的に判断し、併用の是非や期間を決定します。市販薬を使っている場合も、薬局で薬剤師に相談するか、事前に医療機関に問い合わせることが望まれます。
整形外科での標準的な使い方
整形外科では、次のような使い方が比較的一般的です:
- ロキソニン錠(1日2~3回)を服用しつつ、患部にモーラステープを1日1回貼付する
- 急性期(強い炎症を伴う時期)は内服と外用を併用し、数日で外用のみに切り替える
- 慢性の肩こりには、まず湿布薬単独で反応を見る
このように、薬の使い方は「痛みの程度」「炎症の有無」「副作用リスク」のバランスを見ながら段階的に決められるのが一般的です。
実際に効いた?患者の声と臨床的な評価
ロキソニンやモーラステープが肩こりに効くかどうかは、個人差が大きく、すべての患者に万能というわけではありません。しかし、実際にこれらを使用して症状が軽減したという声は多く、特に急性の肩の痛みに対して有効性が認められています。この章では、臨床現場のデータや患者の体験談、医療従事者の評価をもとに、ロキソニンおよびモーラステープの実際の効果について解説します。
医療機関での症例紹介
整形外科クリニックでは、肩の筋肉の急な炎症や外傷後の疼痛管理において、モーラステープとロキソニンの併用が頻繁に用いられています。たとえば、肩甲骨周辺の筋肉痛を訴える30代女性に対し、ロキソニン内服とモーラステープ貼付を5日間続けた結果、痛みの程度(VASスコア)が8から3に改善したという報告があります。臨床医のコメントとしても、「軽度~中等度の炎症が関与している肩こりには、NSAIDsによる薬物療法が非常に有効」と評価されるケースが多く見られます。
SNSやアンケート調査のデータ
SNSや医療系Q&Aサイトなどを調べると、「湿布を貼った直後から肩が軽くなった」「1週間続けたら肩こりが気にならなくなった」など、ポジティブなレビューが多数確認できます。一方、「モーラステープでかぶれた」「ロキソニンを飲んでも効かなかった」といった否定的な意見もあり、使用感には個人差があることがわかります。
ロキソニン・モーラステープが効かない肩こりとは?
ロキソニンやモーラステープを使用しても肩こりの改善が見られない場合、それは単なる筋肉の炎症や緊張とは異なる要因が隠れている可能性があります。薬が効きづらい肩こりの背景には、筋膜性疼痛症候群や神経性の痛み、あるいは心理的ストレスなどが関与しているケースもあり、根本原因の見極めが重要です。
筋膜性疼痛症候群(MPS)との違い
筋膜性疼痛症候群(MPS)は、筋膜と呼ばれる結合組織が緊張・癒着し、痛みを引き起こす状態です。肩こりが慢性化し、特定の部位を押すと強い痛みを感じる「トリガーポイント」が存在する場合は、MPSの可能性が高く、ロキソニンや湿布薬では十分な効果が得られないことがあります。
このような症状には、トリガーポイントへの鍼治療や筋膜リリース、徒手療法などが有効とされ、薬物療法だけでは限界があるため、理学療法士や整体師との連携が求められます。
頚椎症や胸郭出口症候群の可能性
頚椎症や胸郭出口症候群など、神経の圧迫が原因となる肩こりも薬が効きにくい代表的なケースです。頚椎の変形により神経根が圧迫されると、肩から腕にかけての痛み・しびれ・筋力低下を伴うことがあり、湿布や鎮痛薬では根本的な解決には至りません。
また、胸郭出口症候群では、鎖骨周辺で神経や血管が圧迫され、肩こりのほかに腕のだるさや冷感が現れます。これらの症状には整形外科での画像診断や神経学的評価が必要であり、薬物療法の適応を超える場合には手術や装具療法、理学療法の検討も必要になります。
精神的ストレス・自律神経の関与
心理的ストレスが原因で交感神経が過剰に働き、筋肉の緊張を高めることで肩こりが生じるケースもあります。このようなタイプの肩こりでは、痛みの原因が炎症ではなく神経系の緊張やストレス反応にあるため、ロキソニンなどのNSAIDsはあまり効果を発揮しません。
自律神経失調に伴う肩こりでは、ストレスコントロール、生活習慣の改善、睡眠の質向上、必要に応じて漢方薬や抗不安薬の処方が効果的な場合もあります。薬の効果が薄いと感じる場合は、こうした非炎症性の原因を疑い、心療内科や専門外来での相談も検討すべきです。
薬以外の肩こり対策と併用療法
ロキソニンやモーラステープは肩こりの症状を一時的に緩和する有効な手段ですが、それだけでは根本的な改善にはつながらないケースも多く存在します。薬物療法に頼りすぎず、日常生活に取り入れられる非薬物療法やセルフケアを組み合わせることで、肩こりの再発防止や体質改善を目指すことが重要です。
筋膜リリースとストレッチの有効性
筋膜リリースとは、筋肉を覆っている筋膜の癒着をほぐし、滑走性を改善することで血流や可動域を改善する手技療法です。フォームローラーやテニスボールなどを用いたセルフ筋膜リリースでも効果が期待できます。肩甲骨まわりの筋膜を柔らかく保つことで、筋緊張が和らぎ、肩こりの再発リスクが軽減されます。
加えて、僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋といった主要筋に対するストレッチも、筋肉の柔軟性向上と神経系のリラクゼーションに役立ちます。ストレッチは毎日続けることが重要で、入浴後など体が温まっているタイミングで行うのが効果的です。
整体・鍼灸の役割と相乗効果
整体や鍼灸は、身体全体のバランスや自律神経の調整を通じて、肩こりの根本的な改善をサポートします。整体では骨格や姿勢の歪みを整えることで筋肉の負担を軽減し、鍼灸ではツボを刺激することで血流促進・鎮痛効果・神経緊張の緩和が期待されます。
これらの代替療法は、医薬品との併用によって相乗的に効果を高めることが可能です。例えば、薬で一時的に痛みを抑えている間に、整体で姿勢改善や筋膜調整を行うことで、薬が不要な状態へと体質を変えていくことが可能になります。
有酸素運動と呼吸法の重要性
ウォーキングやスイミングなどの軽度な有酸素運動は、全身の血流を改善し、肩まわりの緊張を和らげる効果があります。1日20〜30分の軽い運動でも、筋肉中の老廃物が流れやすくなり、慢性肩こりの症状緩和に役立ちます。
さらに、深呼吸や腹式呼吸などの呼吸法は、副交感神経を優位にして筋緊張を和らげる作用があります。ストレスや不安が強い人には、リラクゼーションを兼ねた呼吸法の習慣化がとくに有効です。
医師の診察を受けるべき症状とは?
肩こりは多くの人が経験する身近な不調のひとつですが、すべてが「疲れ」や「姿勢の悪さ」で片づけられるものではありません。中には重大な病気や神経症状が背景にあることもあり、医療機関での適切な診断と治療が必要となるケースがあります。以下に、自己判断で薬を使うだけでは危険な症状のサインと、受診すべきタイミングを詳しく解説します。
ただの肩こりではない危険な兆候
以下のような症状がある場合は、単なる肩こりではなく、深刻な病態の一部である可能性があります:
- 肩や首の痛みと同時に腕や手がしびれる
- 手に力が入らない、物を落としやすくなった
- 一方の肩だけに強い痛みが集中している
- 頭痛や吐き気、めまいを伴う
- 発熱や倦怠感を伴う肩の痛み
これらの症状は、頚椎症性脊髄症、椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群、さらには心筋梗塞などの内臓疾患による放散痛の可能性も否定できません。早期の受診と画像診断が求められます。
ロキソニンや湿布で改善しないときの選択肢
市販薬や処方薬を一定期間使用しても改善が見られない場合、薬では対応できない別の原因がある可能性を考慮すべきです。痛みが3〜5日以上継続する、または薬の効果が一時的で再発を繰り返す場合には、整形外科での精密検査を受けることを強く推奨します。
MRIやCTなどの画像検査により、神経の圧迫や骨格の異常を特定し、必要に応じてブロック注射、リハビリ、手術といった専門的な治療が検討されます。
整形外科・リハビリ・神経内科への受診目安
- 神経症状(しびれ・脱力・反射異常)がある → 神経内科、整形外科
- 姿勢・動作に関連した筋肉の痛み → 整形外科、リハビリ科
- 疑わしい内臓の放散痛(胸痛・背部痛) → 内科・循環器内科
また、薬物療法だけで対処が難しい慢性肩こりには、リハビリテーションや理学療法の併用が非常に有効です。診断の結果に応じて多職種によるチームアプローチが行われることもあります。
よくある疑問Q&A
ロキソニンやモーラステープを使った肩こり対策について、多くの方が抱く具体的な疑問や不安に対して、専門的かつわかりやすくお答えします。ここでは代表的な質問を10項目まとめてご紹介します。
Q1. ロキソニンとモーラステープは同時に使っても大丈夫?
A. 医師の指示があれば併用は可能です。ただし、どちらもNSAIDsであるため、併用によって体内の総NSAIDs量が増え、胃腸や腎臓への負担が懸念されます。自己判断ではなく、医療従事者の指示に従うことが重要です。
Q2. ロキソニンは空腹時に服用してもいいですか?
A. 推奨されません。空腹時に服用すると胃粘膜への刺激が強まり、胃痛や胃炎、潰瘍のリスクが上がります。食後に服用するようにしてください。
Q3. モーラステープは市販されていますか?
A. モーラステープは医療用医薬品のため市販されておらず、医師の処方が必要です。市販薬としては、ケトプロフェンを含む類似の湿布がありますが、効果や副作用リスクには違いがあります。
Q4. ロキソニンや湿布はどのくらいの期間使ってもいいですか?
A. 通常はロキソニンの連用は3~5日が目安です。それ以上続ける場合は医師の診察を受けるべきです。モーラステープも同様に、長期間使用すると皮膚トラブルなどのリスクがあります。
Q5. 湿布だけで肩こりは治りますか?
A. 湿布は痛みの緩和には有効ですが、根本治療にはなりません。姿勢改善、筋肉のストレッチ、生活習慣の見直しと組み合わせることが重要です。
Q6. モーラステープを貼った部分が赤くかゆくなったのですが?
A. 使用をすぐに中止し、患部を洗浄してください。症状が続く場合は皮膚科受診をおすすめします。光線過敏症や接触性皮膚炎の可能性もあります。
Q7. ロキソニン服用中にアルコールを飲んでも大丈夫?
A. 推奨されません。ロキソニンとアルコールの併用は、胃腸障害や肝機能への負担を高める可能性があります。
Q8. モーラステープを貼ったままお風呂に入ってもいいですか?
A. 入浴中は成分が過剰に吸収されたり、かぶれの原因になることがあるため、入浴前にはがしてください。
Q9. モーラステープを貼った部位が日に当たったらどうなる?
A. ケトプロフェンには光線過敏症の副作用があるため、貼付部位は必ず衣服などで覆って紫外線を避けてください。
Q10. 市販の湿布薬と病院で処方される湿布薬の違いは?
A. 医療用湿布薬は有効成分の濃度が高く、効果も強い反面、副作用リスクもあります。市販薬は副作用リスクを下げてある分、作用も穏やかです。使用目的に応じて選びましょう。
市販薬と処方薬の違いと注意点
肩こりに使われる薬には、市販薬と医療機関で処方される処方薬の2種類があります。どちらも一見似たような名前で販売されていたり、同じ成分が含まれていたりしますが、その効果や使い方、安全性には明確な違いがあります。この章では、両者の違いを医学的観点から整理し、使用する際の注意点についても詳しく解説します。
主な違いは「成分濃度」「添加物」「使用対象」
市販薬と処方薬の最大の違いは、主成分の濃度と効果の強さです。たとえば、ロキソニンS(市販薬)と医療用ロキソニン(処方薬)はどちらもロキソプロフェンを含んでいますが、処方薬の方が純度や濃度の面でより高く設計されており、効果が強く現れることが一般的です。
また、市販薬には一般消費者向けに胃粘膜保護成分などの添加物が含まれていたり、添付文書により厳しい使用制限が設けられているケースもあります。処方薬は医師の判断のもとで使用されることを前提としているため、より個々の症状に合わせて調整が可能です。
市販薬を選ぶ際の注意点
市販薬を購入する際は、成分表をよく確認し、自分の体質や既往症と照らし合わせて安全に使えるかを判断する必要があります。特に以下の点には注意が必要です:
- 胃腸が弱い人はNSAIDsの内服薬(ロキソニンSなど)を避け、外用薬を優先する
- アレルギー体質の人は添加物の種類をチェックする
- 同じ成分の薬を重複して使わない(例:内服薬+外用薬)
薬剤師に相談することで、相互作用や安全性に関するアドバイスを受けることができ、より安心して市販薬を利用できます。
処方薬のメリットとリスク
処方薬の最大のメリットは、医師の診察・診断に基づいて使用されることです。症状の原因が明確にされ、最適な薬が選ばれることで、より高い治療効果が期待できます。また、副作用や他の薬との併用リスクについても医師が把握しているため、安心感があります。
一方で、処方薬は効果が強いため、副作用も発現しやすくなります。ロキソニン錠の長期連用による胃潰瘍、モーラステープによる光線過敏症や皮膚炎などが代表的です。定期的な通院や診察が必要な点も留意すべきポイントです。
肩こりと生活習慣の関係
慢性的な肩こりは、薬や治療法だけでなく、日々の生活習慣とも密接に関係しています。いくら薬を使っても、日常の姿勢や運動、食事、ストレス管理が適切でなければ根本的な改善にはつながりません。この章では、肩こりの発生と悪化に影響する代表的な生活習慣要因と、それに対する実践的な改善アプローチを解説します。
姿勢と座り方
デスクワークやスマートフォンの使用が日常化する現代において、長時間にわたる前傾姿勢は肩こりの最大の原因の一つです。特に「頭部前方位(フォワードヘッドポスチャー)」になると、頭の重さを支えるために首・肩周囲の筋肉が過剰に働き、慢性的な筋緊張を招きます。
正しい座り方のポイントは以下のとおりです:
- 骨盤を立てて座る
- 頭のてっぺんが天井から引っ張られるような感覚を意識する
- モニターの高さは目線と同じか、やや下に調整
- 肘と膝は90度に曲げ、足裏は床にぴったりとつける
運動不足と筋力低下
肩こりに悩む人は、運動習慣が少ないケースが多く、肩周囲の筋力や柔軟性が低下しています。とくに背筋群、肩甲骨周囲筋、体幹筋の筋力低下は、正しい姿勢の維持を困難にし、肩こりを悪化させる原因になります。
推奨される運動習慣:
- 1日30分のウォーキングや軽いジョギング
- 週2〜3回のストレッチまたはヨガ
- 自重トレーニングによる肩甲骨の可動域改善
食生活と水分摂取
筋肉の代謝や神経伝達には、マグネシウムやビタミンB群、タンパク質などが必要不可欠です。インスタント食品や糖質中心の食生活は、筋肉の回復を妨げ、血流を悪化させます。
肩こり改善におすすめの栄養素:
- ビタミンB1(豚肉、玄米、大豆)
- マグネシウム(バナナ、ナッツ、豆類)
- オメガ3脂肪酸(青魚、えごま油)
加えて、筋肉の柔軟性維持には水分補給も重要です。目安として、1日1.5~2Lの水分摂取が推奨されます。
ストレスと自律神経の乱れ
ストレスが蓄積すると、交感神経が優位になり、筋肉が常に緊張状態に置かれやすくなります。特に、精神的プレッシャーが多い現代人にとって、ストレス性の肩こりは珍しくありません。
対策としては:
- 1日10分間の深呼吸や瞑想
- 睡眠の質を高める就寝前の習慣(スマホを見ない、温かいお風呂に入る)
- 趣味や自然との触れ合いによるリラックス
ロキソニン・モーラステープ使用時のチェックリスト
ロキソニンやモーラステープは、肩こりの痛みや炎症を緩和するために有効な治療手段ですが、使用に際しては副作用や誤使用のリスクにも注意が必要です。この章では、正しく安全に使用するためのチェックポイントを一覧形式で紹介します。
使用前に確認すべきこと
- □ 医師または薬剤師に相談したうえで使用している
- □ 現在、他のNSAIDs(内服・外用)を使用していない
- □ 胃潰瘍・腎疾患・アスピリン喘息などの持病がない
- □ 妊娠中または授乳中ではない(使用の可否を確認済み)
- □ 使用部位に傷、湿疹、かぶれなどがない
使用中の注意点
- □ ロキソニンは食後に水またはぬるま湯で服用している
- □ モーラステープは1日1回、決められた時間だけ使用している
- □ モーラステープ貼付部は直射日光にさらさないようにしている
- □ 貼付部に発赤・かゆみ・かぶれが出た場合はすぐに使用を中止している
- □ ロキソニン服用後にアルコールを摂取していない
使用後のセルフチェック
- □ 症状が改善してきたか(痛みの程度、可動域の変化)
- □ 連続使用日数が5日を超えていないか
- □ 皮膚に色素沈着や水疱など異常が出ていないか
- □ 他の健康状態(胃痛、頭痛、倦怠感など)に変化がないか
- □ 症状が再発していないか
「つらい肩こりを放置しないこと」「正しい知識と判断で薬を使うこと」「体質改善に向けた継続的な取り組み」が、あなたの健康な毎日を支える鍵となります。
今後の生活にぜひ今回の情報を役立ててください。
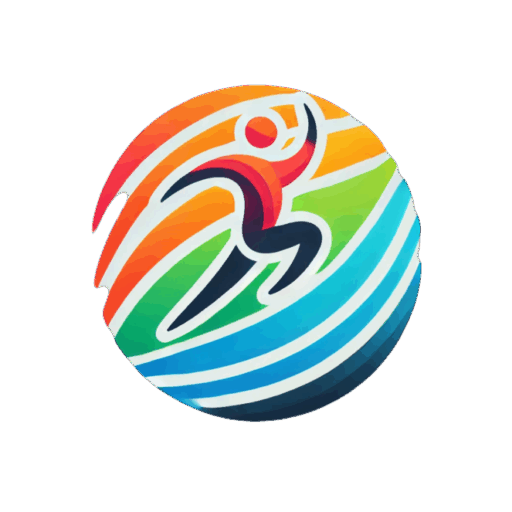




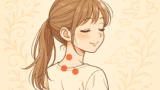

コメント